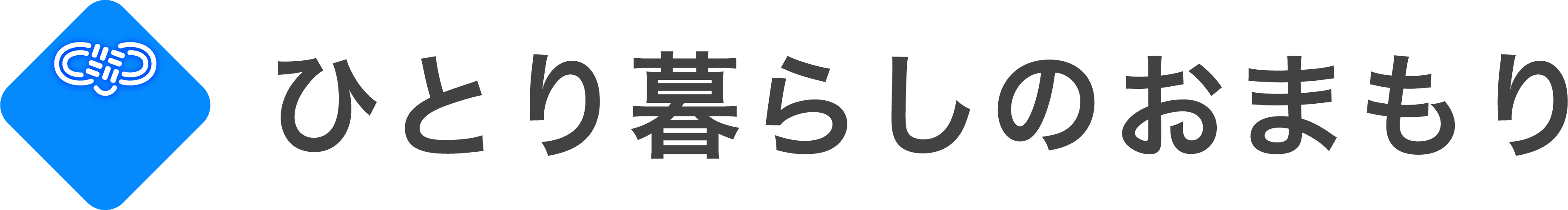加齢と共に、体力の低下などから、健康へのリスクが高まりますが、中でも特に注意したいのが、骨折です。というのも、整形外科医の三浦先生をはじめとした多くの医師が、高齢者が骨折した場合、回復までに時間がかかり、QOL(生活の質)に大きな影響を与え、場合によっては、寝たきりになるきっかけとなることもあるからです。
そこで、今回の記事では、高齢者が骨折しやすい原因、起こりやすい骨折、そして予防策をご紹介します。
(参考:『高齢者に多い骨折の部位を解説|治癒期間や手術ができない場合について』)
見守りサービスという選択肢も!
高齢者が骨折しやすい理由とは
高齢者が骨折しやすい理由には、主に以下の3つがあります。
1.骨量の低下
加齢により、骨量が低下する原因の一つに、骨の『破骨細胞』と『骨芽細胞』の新陳代謝が乱れることが挙げられます。『破骨細胞』は、古くなった骨を溶かす『骨吸収』を行います。一方、『骨芽細胞』はカルシウムなどを付着させて骨を造る『骨形成』を行い、骨を修復していきます。年齢を重ねると共にホルモンバランスが崩れると、『破骨細胞』による『骨吸収』が『骨形成』を上回るようになり、骨密度が減少してしまいます。破骨細胞による「骨吸収」が「骨形成」を上回るようになって、骨量(骨密度)が減ってしまうのです。
『破骨細胞』の働きをコントロールしているのが、女性ホルモンの『エストロゲン』です。特に女性は、閉経前後になるとエストロゲンが減少するため、『破骨細胞』の働きが『破骨細胞』を上回る傾向にあり、骨密度の低下につながります。
更に、加齢により、胃酸分泌量の低下や、腸管でのカルシウムの吸収が悪くなったり、尿へのカルシウム排泄の増加カルシウム、カルシウムの吸収を助けるビタミンDをつくる働きが弱くなるなども、骨量の減少を引き起こす要因です。
このように、骨密度が下がると骨がスカスカになる骨粗しょう症を引き起こし、ちょっとしたはずみで骨折を引き起こすこともあります。
2.運動不足
加齢により、立っている時や動いている時の姿勢を維持するバランス能力が鈍り、転倒しやすくなるのも骨折につながる原因です。
バランス能力は、加齢による運動機能の低下以外にも、脳卒中などの病気によって起こることもあります。
特に注意したいのが、運動不足による悪循環です。運動不足で、筋力が落ちるとバランス能力が低下し、転倒しやすくなります。さらに、骨は負荷がかかるほど、骨をつくる細胞が活性化するため、身体を動かさないと骨が衰えやすくなります。当然のことながら、骨が弱い状態で転倒すると骨折する可能性が高くなるので、運動不足を予防することが重要です。詳しくは後の予防対策で説明します。
3.皮膚菲薄化
加齢により皮膚を形成する表皮、真皮、皮下組織の薄くなり、皮下脂肪が減少します。転倒時に骨を守るクッション機能を果たしている皮膚脂肪が低下すると、骨折しやすくなります。皮膚菲薄化の主な原因には、皮膚の栄養不足と紫外線があります。健康な皮膚を保つには、ビタミンA、C、E、亜鉛などが必要ですが、加齢で食が細くなると、これらの栄養素が不足し皮膚菲薄化につながります。
(参考:『高齢者の骨はもろい?骨を弱くする危険因子と骨の健康を守る方法』/『年齢とともに増加する骨粗しょう症』/『イソフラボンのチカラ』/ )『【はじめての方へ】高齢者の骨折|70代から急増するワケとその予防法』/『皮膚菲薄化型たるみの原因と治療法』)
高齢者のよくある骨折の種類
高齢者のよくある骨折は以下の表にある4か所です。それぞれその原因についても説明します。

1. 橈骨遠位端(とうこつえんいたん)骨折
手首の骨折です。転倒して手をついた時の衝撃により起こりやすいです。
2. 脊椎圧迫(せきついあっぱく)骨折
背骨の骨折です。背骨は、円盤のような骨が積み重なった構造をしてますが、骨粗しょう症が進んでいると、普段の生活動作の中でこの円盤がつぶれて「いつのまにか骨折している」ということもあります。さらに、転倒した際、尻もちをつくことで脊椎圧迫骨折が起こることもあります。
3. 上腕骨近位部(じょうわんこつきんいぶ)骨折
腕の付け根の骨折です。転んで肩を直接打ったり、肘や手をついた時に起こります。
4. 足の付け根の骨折:大腿骨近位部(だいたいこつきんいぶ)骨折
太ももの付け根の骨折です。転倒によって起こります。大腿骨近位部が骨折すると、足で体重を支えることができなくなり、歩けなくなります。歩けないことで、筋力が落ち、これきっかけとなり、寝たきりになってしまう場合があります。実際、整形外科医の佐野先生によると、 寝たきりや要介護になる原因の4分の1が、この大腿骨近位部骨折だと言います。
(参考:『高齢者に多い4つの骨折と予防・ケアについて』/『大腿骨近位部骨折』)
骨折の予防策とは
骨折を予防するには、骨を丈夫にする生活習慣を心がけることが重要です。具体的な予防策として、主に以下の3つがあります。
1.丈夫な骨づくりに必要な栄養素を摂る
丈夫な骨をつくるために必要な3大栄養素は、カルシウム、ビタミンD、ビタミンKです。それぞれ詳しく説明します。
①カルシウム:骨の材料
厚生労働省による「日本人の食事摂取基準」によると、高齢者のカルシウム推奨摂取量は以下のように設定されています。
| 年齢 | 性別 | カルシウム推奨摂取量 (mg/日) |
|---|---|---|
| 65~74歳 | 男性 | 750mg |
| 女性 | 650mg | |
| 75歳以上 | 男性 | 700mg |
| 女性 | 600mg |
次に、どのような食品にカルシウム量が多く、またどのくらいの量を摂取できるのか見てみましょう。
| 食品例 | 食品の目安重量 | カルシウム量 | 特徴 |
| 牛乳 | 200ml | 220mg | 飲みやすい |
| ヨーグルト | 100g | 120mg | のど越しが良い |
| プロセスチーズ | 20g | 140mg | 少量でも多くのカルシウムが摂取できる |
| しらす干し | 30g | 180mg | 小さく食べやすい |
| 干しエビ | 10g | 150mg | 小さく食べやすい |
| 木綿豆腐 | 100g | 150mg | 柔らかく食べやすい |
| 小松菜(茹で) | 100g | 170mg | 柔らかく食べやすい |
これらの食品の特性を理解した上で、自分の好みに合わせて日々の食事にバランスよく取り入れることで、効果的にカルシウムを摂取することが重要です。
②ビタミンD:腸管からのカルシウムの吸収を助ける
同じく、厚生労働省による「日本人の食事摂取基準」によると、高齢者のビタミンD推奨摂取量は以下のように設定されています。なお、カルシウムの摂取量と異なり、男女差、また65~74歳と75歳以上での差がありませんでした。
| 年齢 | 性別 | 推奨摂取量 (㎍/日) |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 男性 | 8.5㎍ |
| 女性 | 8.5㎍ |
次に、どのような食品にビタミンD量が多く、またどのくらいの量を摂取できるのか見てみましょう。
| 食品例 | 食品の目安重量 | ビタミンD量 | 特徴 |
| まいたけ(生) | 100g | 4.9㎍ | 柔らかく食べやすい* |
| あんこう肝(生) | 60g | 110㎍ | 柔らかく食べやすい |
| しらす干し | 5g | 61㎍ | 小さく食べやすい |
| 鶏 卵黄(生) | 1個:約16g | 12㎍ | のど越しが良い |
| べにざけ(生) | 1切れ:約80~150g | 33㎍ | 細かくして食べいやすい* |
*調理後
後述するように、ビタミンDは食品からだけでなく、日光を浴びることで生成されます。しかしながら、加齢により、皮膚におけるビタミンD生成能力が低下し、また人によっては、外出をする機会が減少し、日に当たる時間が十分でないこともあります。そのような場合、ビタミンDを食事から意識的に摂取することが重要です。
③ビタミンK:体内に取り込んだカルシウムの骨沈着の際に必要
上記と同資料の「日本人の食事摂取基準」によると、高齢者のビタミンK推奨摂取量は以下のように設定されています。またビタミンDと同じく、男女差、また65~74歳と75歳以上での差がありませんでした。
| 年齢 | 性別 | 推奨摂取量 (㎍/日) |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 男性 | 150㎍ |
| 女性 | 150㎍ |
ビタミンKは、脂溶性であるため、油と一緒にとると吸収率が上がるため推奨されています。
主に、以下のような食品にビタミンKが多く含まれており、食べやすさなどの面からも高齢者にお勧めです。
| 食品例 | 食品の目安重量 | ビタミンK量 | 特徴 |
| カットわかめ(乾) | 10g | 1,600μg | のど越しが良い* |
| ほうれんそう(葉 通年平均・生) | 20g | 270μg | 柔らかく食べやすい* |
| 挽きわり納豆 | 1パック:30~50g | 930μg | 小さく食べやすい |
| ナチュラルチーズ パルメザン | 6g(大さじ1) | 15μg | 細かく食べやすい |
| 鶏 卵黄(生) | 1個:約16g | 39μg | のど越しが良い |
| 鶏肉(皮つきもも生) | 1枚:200~300g | 29μg | 柔らかく食べやすい* |
*調理後
【骨折を効率よく防ぐには『しらす納豆ご飯』】
このように骨を丈夫にする多様な食品がある中、一人暮らしだと「手のかかる料理は面倒・・・」「火の消し忘れが怖くて、加熱する料理をあまり作らない・・・」ということがあるかもしれません。
そこで、手軽に骨を丈夫にする料理としてお勧めしたいのが、「しらす納豆ご飯」です。
松原リウマチ科整形外科によると、カルシウムが宝庫なしらすを、消化を助ける納豆と食べると吸収率がアップするといいます。
さらに、上記にもご紹介したように、ビタミンKは、特に納豆に多く含まれています。公益財団法人長寿科学更新財団によると、納豆を日常的に食べている人は、そうでない人と比較して、ビタミンKの摂取量が約2倍であるというデータがあると述べています。
手軽かつ効率よく骨を丈夫にする食事として、『しらす納豆ご飯』を是非普段の生活に取り入れてみてください。
2.適度な運動
骨の健康な状態を保つためには、骨に適度な刺激を与える運動をすることが重要です。しかしながら、高齢者の場合、長距離を走るなど、心臓や足腰に過度な負担がかかりすぎないよう注意が必要です。ウォーキングや軽いジョギングなどに加えて、自宅でもできる手軽な体操もあるので、以下の動画を是非参考にしてみてください。
自分にあった無理なく続けられる運動を生活に取り入れることをお勧めします。また、関節に何らかの疾患がある方や、病気を治療中の方は、主治医と相談してから適切な運動を始めることも重要と言えるでしょう。
3.適度に日光に当たる
上記の骨を丈夫にする栄養素でご紹介したように、日光を浴びることでカルシウムの吸収を助けるビタミンDが体内で生成されます。
もちろん、日光の浴びすぎは、紫外線による皮膚や目への健康被害につながるので、『適度な日光浴』が重要です。
ですが、『適度な日光浴』とはどの程度なのでしょうか?原宿リハビリテーション病院の林先生によると、夏であれば暑さを避けて、木陰で30分程度過ごすだけで十分だといいます。また冬であれば30分~1時間程度散歩に出かけると良いとのことです。
しかしながら、屋内で過ごす時間が長い高齢者は、特にビタミンD不足が懸念されると指摘されています。そこで、できるだけ1日に1回は外出する機会をつくる、また気候や体調の関係でそれが難しい場合は、上記にご紹介したように、ビタミンDの多く含まれた食品から栄養を摂ることが望ましいでしょう。
(参考:『【完全ガイド】高齢者のカルシウム摂取 必要量と食品での効果的な摂取法は?』/『骨を強化する「骨トレ」で、健康な骨を目指す!』/『高齢者の骨はもろい?骨を弱くする危険因子と骨の健康を守る方法』/『毎日の食事で丈夫な骨をつくるために』/『日本人の食事摂取基準(2020年版):高齢者』/『ビタミンDの働きと1日の摂取量』/『ビタミンKの働きと1日の摂取量』/『骨を強くする食事』)
「ひとり暮らしのおまもり」という選択肢も
普段から健康に気を付けていても、何かの拍子で転倒してしまうということもあるかもしれません。西陣病院の中村先生によると「転倒して痛い時は迷わず整形外科へ」と言います。というのも高齢者の場合、骨折が原因で自立的な生活が難しくなることが多いからです。
しかしながら、重篤な転倒の場合、動けなくなってしまうということもあるかもしれません。そこでお勧めしたいのが、高齢者の見守りサービス『ひとり暮らしのおまもり』です。『ひとり暮らしのおまもり』には、オプションの『ケアウォッチ』があり、左右についているボタンを同時に押すと、見守る側のスマホに大きな音でアラートを送ることができます。
いざという時に、家族に助けを求められるように、手軽に導入できる高齢者見守りサービスをご検討してみてはいかがでしょうか。
(参考:『転倒して痛い時は迷わず整形外科へ』)
- 工事不要の見守りサービス
- 落とし物防止に使われているIoT技術を採用
- 月額費用がかからず9,240 円(税込)と低額*
*オプションのケアウォッチをつけた場合、合計13,200 円(税込)