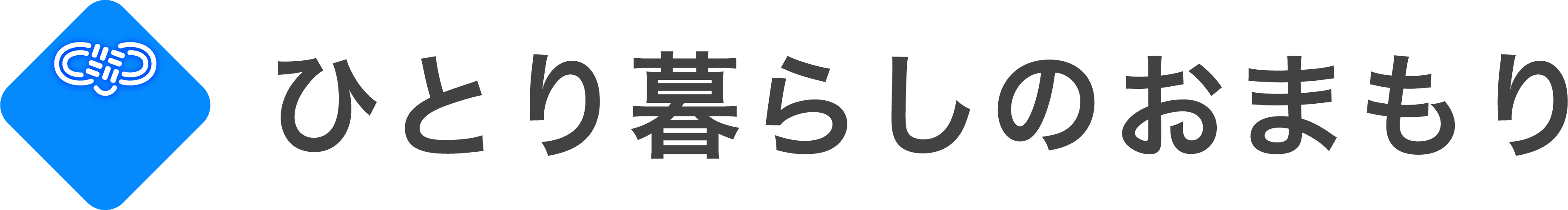「高齢者は特に熱中症に気を付けた方がいい」ということを一度は聞いたことがあるという方がほとんどではないでしょうか。実際に、 2024年5-9月の消防庁による統計データによると、熱中症で救急搬送された人のうち65歳以上の高齢者が57.4%と6割近くを占めていました。またその割合は、前年に比べて2.5ポイント増と、高齢化社会が進むにつれ増加傾向にあることが明らかになりました。
そこで今回のコラムでは、高齢者がどのようにしたら熱中症を予防できるか解説します。
(参照元:2024年5-9月の熱中症による救急搬送患者は9万7578人で過去最高、120名が死亡、2178名が3週間以上入院—総務省消防庁)
見守りサービスという選択肢も!
高齢者が熱中症になりやすい理由とは
そもそも、高齢者はなぜ熱中症になりやすいのでしょうか?以下に主な4つの理由をご紹介します。
暑さを感じにくくなる
人の皮膚は、温度センサーの機能を果たしています。皮膚が読み取った情報を脳に伝え、発汗の量を調節します。さらに、脳が室温の調整や衣類の着脱といった対処を指示します。しかしながら、老化に伴い皮膚センサーが鈍くなり、暑さを感知しにくくなり、身体機能が適切に働かないだけでなく、温度調節をする行動につながりにくくなります。
実際、環境省の熱中症予防サイトによると、夏季の間、70歳以上の高齢者の住居では、若年者より室温が2℃ほど高い環境で生活しているという報告があると言います。この理由として、高齢者が冷房代を節約している、もしくは冷房を強くかける習慣がないというような説もありますが、一番の理由は温度センサー機能の低下だと同サイトでは指摘しています。
熱放射能力の低下
体温には、手足など外環境の影響を受けやすい「皮膚温」と、脳や臓器など体の中心部の「深部体温」があります。ご存知のように人の身体は、体温が上がった時に、水分を汗として放散させることで体温を一定に保っています。この働きを熱放射能力と言いますが、高齢になると、発汗量の増加が遅れ、体に熱がたまりやすくなります。深部体温が上昇すると、熱中症の症状である頭痛、意識がもうろうとする、吐き気や、倦怠感といった症状が引きおこります。
喉の渇きを感じにくくなる
環境省のリサーチ結果によると、高齢者が若年者と同じくらい汗をかいた場合でも、高齢者の方が脱水状態に陥りやすく、回復しづらいということが明らかになっています。通常、人は脱水が進むと、のどの渇きを感じ、自然に水分補給をします。しかしながら、高齢者は脳での察知能力が低下しており、渇きを感じず、十分な水分補給をせずに脱水につながると言います。脱水症状になると、体内の水分の量が減ると、血液の量も減ってしまい、腎臓への血流が低下し、老廃物や余分な塩分や水分の排泄機能が低下します。特に加齢により腎臓機能が低下している場合、一旦脱水症状になるとリカバリーに時間がかかるということが指摘されています。
もともとの体液量が少ない
成人の身体の約55~60%は水分ですが、加齢とともに実質細胞数が減るため、高齢者の水分含有量は50%まで低下します。汗をつくるための水分が、もとから若い時と比較して少ないため、高齢になると脱水症状になりやすくなります。それでは、一日にどのくらいの量の水分を摂取すれば良いのでしょうか。長寿科学振興財団によると、水の必要量は性別、年齢、身体活動レベル別に算定するための科学的根拠は今のところ十分整っていないと言います。しかしながら、水分はわずかに不足するだけで、以下のような症状が現れるといいます。
・1%の損失:のどの渇き
・2%の損失:めまいや吐き気、食欲減退
・10~12%の損失:筋けいれん、失神
・20%の損失では生命の危機
つまり、水分はわずか2%でも損失されると健康状態が脅かされてしまいます。
(参考:『高齢者と子どもの注意事項』/『水は1日どれくらい飲めば良いか』『高齢者の体温調節機能が低下する理由と対策方法』/『運動の良い汗と悪い汗』/『深部体温と熱中症』/『脱水には気をつけて(腎臓の機能と脱水の関係)』/『慢性腎臓病(CKD)と塩分の関係』)
熱中症の予防策
高齢になると、健康状態の回復に時間がかかるため、未然に防ぐことが重要です。それではどのような対策をしたら、熱中症にならないのでしょうか。
1.こまめに水分補給をする
上記にお伝えしたように、高齢者はのどの渇きを感じにくいため、こまめに水分を摂ることが重要です。また、入浴前後など汗をかきやすい時も水分補給をするようにしましょう。加えて、「トイレに起きるのが嫌だから...」と睡眠時に水分補給を控える高齢者の方もいますが、寝ている時にも汗をかくため、就寝前、起きた時にも水分を摂ることが重要です。
2.暑さをさける
厚生労働省は、暑さをさけるポイントとして「屋内」「屋外」「自分の身体」の3つを挙げています。
以下にそれぞれの箇所においてどのような工夫が必要かご紹介します。
| 場所 | 工夫 |
| 屋内 |
・風通しをよくする
・遮光カーテン、すだれ等で日光を遮る
・エアコン等で温度調節をする
・温度計で気温をチェックする |
| 屋外 | ・日傘や帽子の着用する ・日陰をできるだけ通るようにする ・こまめに休憩をとる ・暑い日は日中の外出をできるだけ控える |
| 自分の身体 | ・通気性や吸湿性の高い衣服を着用する ・速乾性機能のある衣服を着用する |
先の「高齢者が熱中症になりやすい理由」でお伝えしたように、高齢者は皮膚センサーが衰え、温度の変化を感知しにくくなっています。一般的に室温が28度になったらエアコンをつけることが推奨されているので、温度計がついた置時計などで室温を確認できるようにしておくことをお勧めします。
3.暑さに耐えられる体力をつくる
そこでお勧めなのが、室内でもできる体力づくりです。今、YouTubeで高齢者向けの室内でできる熱中症対策の体操が多く紹介されています。以下に一例を紹介しますが、自分に合ったものを是非取り入れてみてください。
(参考:『暑いなぁ」と感じる前に、熱中症対策』/『熱中症を防ぎましょう』/『室温何度からエアコンつける目安徹底解説|夏冬の適温・快適節電・冷暖房の違いと最新節約術』/『高齢者に適したウォーキングとは』/『高齢者に適したウォーキングとは』)
高齢者が注意したいのは住居での熱中症
しかしながら、どんなに注意をしていても熱中症の症状が出てしまい、場合によっては一人で対処することが難しくなり、周囲の助けが必要になることがあるかもしれません。「熱中症は暑い日に出かけると起こるから、誰かが助けてくれるはず...」と思われるかもしれませんが、実は熱中症は自宅で起きる確率が最も高いということが明らかになっています。
【熱中症の発生場所】

東京メディカルクリニックによると、高齢者は、体温調節機能が低下していたり、暑さやのどの渇きを感じにくくなっているため、特に住居で熱中症になる確率が高いと言います。
(参考:『熱中症について』/『「暑いなぁ」と感じる前に、熱中症対策』)
一人暮らしの高齢者にお勧めの熱中症対策
自宅で急に具合が悪くなったという時のためにお勧めしたいのが、高齢者の見守りサービス『ひとり暮らしのおまもり』です。『ひとり暮らしのおまもり』には、オプションの『ケアウォッチ』があり、左右についているボタンを同時に押すと、見守る側のスマホに大きな音でアラートを送ることができます。
もちろん、熱中症にならないように日頃から健康管理を行うことが最も重要ではありますが、いざという時のために、手軽に始められる見守りサービスのご利用を検討してみてはいかがでしょうか。
- 工事不要の見守りサービス
- 落とし物防止に使われているIoT技術を採用
- 月額費用がかからず9,240 円(税込)と低額*
*オプションのケアウォッチをつけた場合、合計13,200 円(税込)