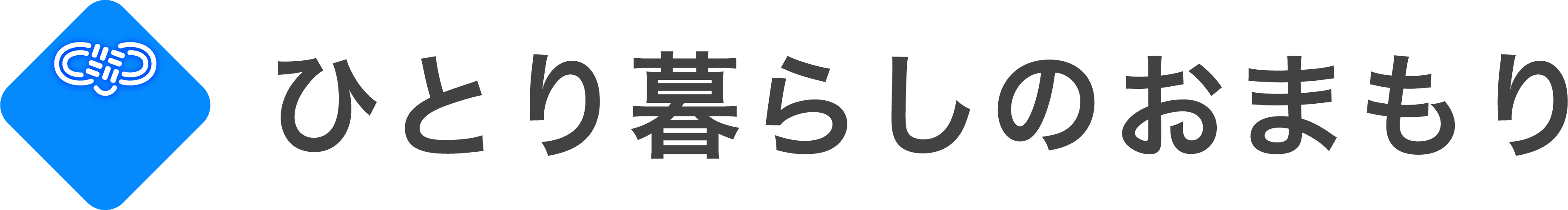親が高齢になるにつれ「将来、介護が心配だ・・・」と不安に感じることはないでしょうか。特に一人っ子の場合「自分だけで面倒を見れるだろうか・・・」と気懸りな方も多いかと思います。実際、国立社会保障・人口問題研究所が実施した「出生動向基本調査」によると、一人っ子の割合は、20年ほど前は10%程度だったのが、2021年には19.7%と2割近くになったというデータがあることから、そのような悩みを抱えている子が増加傾向といえるでしょう。
そこで、今回は一人っ子ならではの介護のお悩みと、いざという時の備えるポイントをご紹介します。
(参考:『一人っ子が急増 過去20年で1割→2割 要因は晩婚化以外にも』)
見守りサービスという選択肢も!
一人っ子ならではの負荷
助け合える兄弟や姉妹がいたとしても、親の介護は何らかの負担がかかるものです。特に一人っ子の場合、どのような負荷がかかる可能性があるのでしょうか?在宅介護エキスパート協会 代表の渋澤氏によると、主に以下の3つがあるといいます。
身体的負荷
高齢者の介護は体力が要ります。そして時として、仕事との両立が難しい状況になります。実際、厚生労働省の雇用動向調査によると、2023年に離職した人介護介護が理由で離職せざる「介護・看護」を理由とする人は約7.3万人で、2000年と比べて約2倍となっているといいます。また、そのうち女性が約77%と圧倒的に多く、年代別では、50歳代が最も多くなっています。
本調査からは、介護離職につながった人に兄弟がいるかどうかは明らかでないのと、高齢化社会が進んでいるという背景もありますが、冒頭でご紹介したように、ここ20年で一人っ子が増えているということから、何らかの相関性があると考えられます。
精神的負荷
・介護と自分の生活を両立するのが難しくストレスが溜まる
経済的負荷
よって、親が年金や貯金を切り崩しても賄うことができない場合は子が親に経済的援助をするしかありません。
公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、介護に適した住宅へのリフォームや、介護用ベッド、車椅子の購入など「一時的にかかる介護の費用」は平均74万円でした。ただし、施設によっては入所する際に、入居一時金が数百万円必要な場合もあります。一方、介護サービスの利用料、福祉用具のレンタル代、おむつなどの介護用品購入費など「毎月かかる介護費用」の平均は8.3万円でした。毎月支給される国民年金の平均額は5万6252円、会社員や公務員などが加入する年金制度である厚生年金の平均額は14万4366円です。
したがって、親が厚生年金に加入していない場合は、毎月約3万円が不足することとなります。
親の貯金と年金で賄うことができるのが一番ですが、そうでない場合、経済的な負担が子にかかる可能性があります。一人っ子の場合、そのような場合に備えて資金を準備しておかなければならないという負荷がかかります。
(参考:『親の介護を一人っ子がするときの基本!直面する3つの不安と解消法とは?』/『【一人っ子の介護】親の介護をするときの5つの不安と解消法|おすすめの介護サービスも紹介』/『介護離職者はどれくらい? 介護離職をしないための支援制度は?』/『サービスにかかる利用料』/『親の介護費用はいくら?子どもの負担を減らす介護費用の備え方』
親の介護に備えて知っておきたい3つのポイント
以下を理解することで、いざという時の介護の負荷を一人っ子でも軽減できます。
介護保険サービスを理解し利用する
| 内容 | デイサービス | デイケア |
| 利用目的 |
・利用者への日常生活支援 |
・利用者の身体機能の回復や維持など、医療的な支援 |
| 対象者 |
・要介護1~5の人 |
・要介護1~5の人 |
| 人員体制 |
・介護職員 |
・医師、看護職員が常駐 ・リハビリの専門職がサービスを提供 |
通所するにあたり、通常送迎サービスも受けられます。さらに車椅子であっても、リフト付きの送迎者で対応してくれるため、親の状況に合わせた対応を期待できます。
さらに、通所サービスを利用することによって、子自身の介護負担を軽減できるだけでなく、親がスタッフや他の利用者と交流することにより、生活習慣病は認知症のリスクの軽減につながります。
| 施設の種類 | 目的 | 入所対象者 |
自己負担(1割)の目安(1カ月:30日の場合)
|
| ・自宅では介護が困難な人(主に寝たきりや認知症の人)が入所 ・日常生活において常時介護が必要な人を支援 |
要介護3以上 |
23,340~27,390円 | |
|
・医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う ・病状が安定している人に対し、在宅への復帰を支援 |
要介護1から5の認定を受けた人 |
23,430円~29,790円 |
|
|
・長期療養のための医療と日常生活上の介護が必要な人が入所 |
要介護1から5の認定を受けた人 |
24,750円~40,710円 |
料金において、どの施設においても共通していることが2つあります。それは、要介護の数値が高いほど価格が高くなるということです。また、食費、居住費、日常生活費は別途負担となります。
一人っ子である場合でも、親の状況に合わせた施設を選択し、適切な介護を受けることで負担を軽減できます。
>関連記事『老人ホームと介護施設は何が違う?高齢者向け施設の種類とその費用をご紹介』
専門家に相談する
親が高齢になるにつれ、定期的にクリニックに通っている方も多いかと思います。かかりつけ医師は、血圧などの日々の体調や、食生活、運動などの暮らし方を全体を診てくれています。親の介護で困ったときは、まずはかかりつけの医師に相談することが望ましいでしょう。
また、病気や怪我による入院がきっかけで介護が必要になる高齢者も少なくありません。そのような場合、大きな病院医療機関内にある相談窓口でも、社会福祉士、精神保健福祉士といった資格を持つ医療ソーシャルワーカーに介護に関する相談ができます。
地域包括支援センター
同センターは、高齢者だけでなく、支える家族や親族も利用でき、病気、介護、金銭的な問題だけでなく、日常生活でのちょっとした心配事まで、多様な相談を受け付けています。多義な内容の相談に対応するため、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)などの資格を持ったスタッフが在籍しており、専門的な知見からアドバイスを受けることができます。
同センターは、原則各市町村に1か所以上設置されており、窓口を含めると全国に7,000以上の施設があるなど地域に密着した支援を受けられます。さらに、総合相談や介護予防ケアマネジメントは、ほとんどの自治体で無料ですので、特に一人っ子にとっては心強い相談相手になるでしょう。
親自身と話し合っておく
さらに国立長寿医療研究センターによると、親が元気なうちに一緒に思い出づくりをすることで、親の認知機能の活性化と楽しかった思い出が精神的な安定にもつながると言います。
(参考:『【在宅介護の強い味方!】デイサービス(通所介護)とは?特徴やサービス内容を表を使って徹底解説』/『地域包括支援センターについて』/『介護サービス(施設サービス)の種類と費用のめやす』/『地域包括支援センター」の役割と利用方法』/『親の介護に直面した時、医師に何を頼れるか。介護と医療の境目は?』/『親のかかりつけ医の上手な頼り方・専門医選びQ&Aも』/『家族との思いでづくりに旅行と考えていますが、もの忘れが激しいので意味のないことでしょうか?』)
「ひとり暮らしのおまもり」という選択肢も
中には「高齢な親が実家で一人暮らしをしているけれども、離れて暮らしていてなかなか様子を見に行けない・・・」という一人っ子の方もいるかもしれません。今は元気にしていても、高齢であると急に具合が悪くなったり、転倒するなどし、早期処置ができなかったことがきっかけで介護が必要な状態になる方も少なくありません。
そこでお勧めしたいのが、高齢者の見守りサービス『ひとり暮らしのおまもり』です。『ひとり暮らしのおまもり』には、オプションの『ケアウォッチ』があり、左右についているボタンを同時に押すと、見守る側のスマホに大きな音でアラートを送ることができます。
介護が必要になる前に、家族に助けを求められるように、手軽に導入できる高齢者見守りサービスをご検討してみてはいかがでしょうか。
- 工事不要の見守りサービス
- 落とし物防止に使われているIoT技術を採用
- 月額費用がかからず9,240 円(税込)と低額*