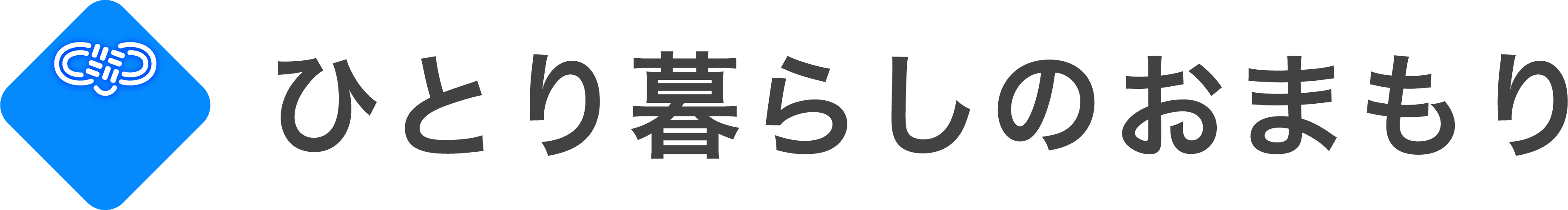「実家に物が多く散らかっている・・・」「親がいらないものをため込んでいる・・・」このようなお話をお伺いすることがよくあります。場合によっては、それが原因で、実家から足が遠のいてしまう、もしくは親と喧嘩になってしまうというようなことも少なくないといいます。
そこで今回のコラムでは、なぜ高齢者が片づけられないのかその理由を明らかにした上で、片づけるためのポイントを事例を交えて考えてみたいと思います。
見守りサービスという選択肢も!
高齢者が片づけられない4つの理由
高齢者が片づけられない理由には以下の4つがあると考えられています。
体力の低下
高齢になると、色々な所に支障が出てきます。例えば、以下のようなことが考えられます。
・肩が痛くて高いところに手が届かない
・膝が痛くてしゃがめない
・歩くのが億劫
・重いものが持てない
このような理由から、部屋を片づけることが物理的にできない、またはできるだけ歩かないで済むようにと椅子回りに物を置く傾向があります。
認知症
認知症が現れ始めると、ゴミの分別ができなくなったり、ゴミの収集日を忘れて、溜め込んでしまったすることがあります。さらに、買ったモノがどこにあるか、もしくは買い置きをしておいたことを忘れてしまい、同じモノをいくつも買ってしまい物が溜まってしまうことがあります。
また、内科医の楠先生によると、認知症が発症すると、ゴミでしかない物を「まだ使える」と判断し、捨てずに集める「収集癖」の症状が起こるケースがあるといいます。
孤独を感じている
心理カウンセラーの佐藤先生によると、孤独を感じている人は、何もないスペースが苦手な傾向にあり、物が回りにあることで安心することがあるといいます。配偶者に先立たれて一人暮らしになった高齢者も、このような孤独感から片づけることができなくなる場合があるとしています。
世代による価値観の違い
戦中戦後のモノのない時代を体験している80代、90代の高齢者は「とりあえず取っておく」ということが習慣化していて、「もったいない」「まだ使える」という感覚が強く捨てることに抵抗感がある傾向があります。
また、昭和の高度成長期を経験した70代は「モノをたくさん買って消費することが幸せ」というバブルの時代を経験しており、身の回りにモノが多くても抵抗感がなく部屋が片付かないということもあるといいます。
それでは、このような親の住まいをどのようにしたら、片づけることができるのでしょうか?5,000軒の片付け実績を持つ安東氏によると、高齢者は、物を捨てることに敏感になっているケースが多いため、NGなのは「捨てよう」という言葉だといいます。『別に片付けなくてもいい』と拒否するだけでなく、親によっては『葬式の準備でもするの?』と不快感を露わにすることもあるといいます。
とはいっても、「実家に帰る度に散らかっているのを見ると嫌な気持ちになる」、また「モノに躓いて転倒するのが心配だ」という子の言い分もあるでしょう。そこで、どのようにすれば親と良好な関係を気づきながら片づけができるのか、実際の事例から改善点等を検証してみたいと思います。
(参考:『ゴミ出しと認知機能』/『心理カウンセラーに聞く、ゴミ屋敷の住人になりやすい人のタイプと傾向』/『高齢の親が片付けできない理由!きれいな部屋にする方法』/『老親の家の片付けは"洗面台下"から始めよ』/『実家のモノ、増えてない??? 親世代はなぜモノをためこんでしまうのか』)
事例から考える実家の片づけ方法
ここでは、実際に子が親の住まいを片づけた事例を3つご紹介します。
事例1:子供達が実家の物を整理
Aさんの70代のお母さまは、25年ほど前に若くして配偶者がなくなり、1人で暮らしています。2人の娘が実家から1時間ほどの場所に住んでおり、最近お母さまに認知症の傾向があることから、定期的に様子を見に行っています。2人の娘はお母さまのご自宅がゴミ屋敷に近い状態にあることを不満に思っていました。
お母さま的には、2人の娘が自宅を片づけたいということをあまり快く思っておらず「いつか使うから」「まだ使えるから」と言っていました。それに対して娘たちは「それなら、掃除を手伝うよ」といって洗面所の下から整理をして行きました。そこには買いだめした古い化粧品などがたくさんあり、使用期限が過ぎているのを母に示してから捨てました。
娘たちは、次に衣類の整理を始めました。お母さまは、数年前まで社交ダンスを習っていましたが、膝を痛めて、辞めていました。「社交ダンス用のドレスなんてもう着ないでしょ。」と娘たちが言いましたが、お母さまは「また着ることがあるかもしれないから。」と言いました。最終的に娘たちは、お母さまのドレスを全て捨てました。ですが、お母さまは認知症であるため、娘たちが捨てたモノへの記憶は特にないため、娘たちも「やっぱりいらなかったんだ」と感じており、満足しているとのことです。
【良かった点】
先にご紹介して、片づけのプロの安東氏によると、実家の片づけは洗面台の下から始めるのが良いといいます。というのも、水回りを清掃しているという印象を親に与えることができ、また不要なものがたくさんあることを可視化して伝えることができるからです。
【更なる改善点】
現在、認知症の進行に対する効果があるとして注目されている心理療法に「回想法」があります。これは、懐かしいモノや映像を見て、自分が元気で若かったころの思い出を回想することで、脳を活性化し、情緒を安定させるという方法です。この観点から考えると、お母さまのお気に入りのドレスの一着くらいはとっておいてあげた方が良かったかもしれません。
(参考:『老親の家の片付けは"洗面台下"から始めよ』/
『回想法とは?近年認知症の進行に対する効果が確認されている【回想法】について解説します。』)
事例2:子が実家の収納方法を改善
Bさんのお母さまは3年ほど前に亡くなり、実家には70代後半のお父さまが一人で暮らしています。Bさんは実家から30分ほどのところに住んでおり、お父さまのために、定期的にご飯を作りに帰っています。ですが、実家の食卓の上に物が置いてあり、食事をするスペースがほとんどないことに不満を感じていました。食卓の上に置いてあるのは文具や薬、近所の方から頂いたお菓子などです。
ある日、その不満を高齢の母親と2人暮らしをしている友人に話すと「年寄は動くのを面倒に感じるし、どこに物を置いたか忘れてしまうから、手と目の届く範囲に物を置きたがるのよ。」と言われました。
Bさんは自分が実家に帰る度に「机の上を片づけてよ!」と親に言っていたばかりでしたが、考え方を改め、収納に工夫をすることにしました。キャスターのついたバスケットタイプのラックを2つ買い、そこに机の上にあったお菓子などを入れるようにしました。その結果、お父さまもあまり動かずに物を取ることができ、Bさんも実家に帰ってお父さまと向き合って、快適にお茶を飲んだりすることができるようになったといいます。
【良かった点】
高齢者にお勧めのキャスター付きでバスケットタイプのラックは、中身も見えやすく、移動もしやすいので、高齢者にお勧めです。
【更なる改善点】
ダイニングテーブルは引き出し付きのものがあります。可能であれば、引き出し付きのダイニングテーブルに買い替え、薬や保険証などを、良く使う物をその中に収納できるようにすると更に良いでしょう。
事例3:外部サービスを利用して片づけを促進
Cさんの70代のお母さまは、一軒家に一人暮らしをしていましたが、高齢になったためよりコンパクトで生活しやすいマンションに引っ越すことにしました。その際に、昔のアルバムや洋服などの収納スペースが足りないという悩みがありました。
そこでCさんは、近所のトランクルームを借り、季節ごとに衣服を入れ替える、またアルバムなど普段見ないものを収納することにしました。
さらに、Cさんは母親の引っ越し祝いにお掃除ロボットを購入してあげました。Cさんのお母さまは、お掃除ロボットをペットのように感じているようで、「今日もお掃除がんばってるわね」など話かけているそうです。また、衣服などを床に置いておくと、掃除中に絡まってしまうため、部屋の整理整頓のモチベーションにもなっているそうです。
【良かった点】
親の「とっておきたい」という意思を尊重し、解決策を自ら提案したのが良かった点であるといえます。
【更なる改善点】
昔のアルバムは台紙に貼るスタイルのものもあり、表紙が分厚いものもあり、重く嵩張ることが多々あります。そのようなアルバムは、トランクルームにとっておいても、出し入れが大変で見る機会が限られてしまうでしょう。そこで、写真をデータ化してくれるサービスなどを活用して、デジタルフォトフレームなどで自宅で見れるようにすると更にお母さまに喜んで頂けるかもしれません。
(参考:『節目写真館』)
高齢者見守りサービスという選択肢も
上記の事例に共通しているのは「高齢の親に安全に安心して暮らしてほしい」という想いだといえます。しかしながら、実家に年に帰るのは1、2回くらいで、その限られた日数で実家の片づけなどはなかなかできないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、高齢の親のために、何かしてあげたいけど、なかなか自分の生活もありできないと気懸りな方にお勧めしたいのが、高齢者の見守りサービスです。
『ひとり暮らしのおまもり』は実家にWi-Fi環境さえあれば、工事不要で、月額費用もかかりません。
さらに、見守る側が複数であっても、各自のスマホから、アプリかLINEの自分が利用しやすい方で見守ることができます。実際、上記事例Aさんのように、高齢で一人暮らしをしている親を姉妹で見守っている利用者の方のインタビュー記事もございますので、是非ご参考にしてみてください。
>関連記事『利用者インタビュー「母と離れて住んでいる私の気持ちが少し楽になりました』
加えて、オプションでSOS発信ができる「ケアウォッチ」を購入することも可能です。「ケアウォッチ」は見守られる側が異常を知らせたい時に左右のボタンを同時に押すと、見守る側のスマホに大きな音でアラートを送るという仕組みです。
実家に一人で住む親の「転倒など、事故が心配だな・・・」と感じたら、『ひとり暮らしのおまもり』を設置されることを是非お勧め致します。
>関連記事:『開発者秘話・裏話①:『ひとり暮らしのおまもり』はどのようにして生まれたのか』
- 工事不要の見守りサービス
- 落とし物防止に使われているIoT技術を採用
- 月額費用がかからず9,240 円(税込)と低額