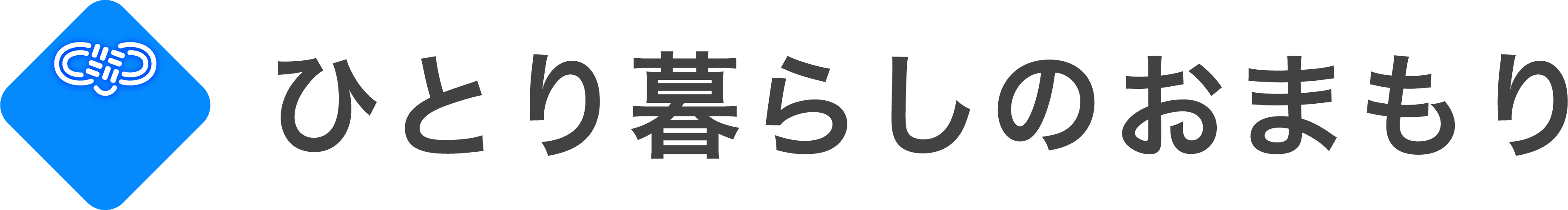高齢の親が今は元気に実家で一人暮らしをしていても「将来、弱って来た時に心配・・・。」と思われたことはありませんか?
厚生労働省は『健康寿命』の定義を「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」としています。とすると、『寿命』と『健康寿命』の差は、日常生活に何らかの支障がある『サポートが必要な期間』となります。
実際、そのような期間はどのくらいあるのでしょうか?
日本における『寿命』と『健康寿命』の平均差は、2019年において男性8.73年、女性12.06年でした。ですので、多くの高齢者が晩年に何だかのサポートを必要としていることがわかります。
もちろん、親がいつまでも自立して生活できていることが理想ではあります。ですが、もし介護が必要になっても、親が住み慣れた自宅で暮らせるように、今回のコラムでは『訪問介護』の利用方法、受けられるサービス、費用といった基本を解説致します。
(参照元:「健康寿命とはどのようなもの?」公益財団法人 生命保険文化センター)
高齢者の自宅での事故は早期発見が重要!見守りサービスという選択肢も!
『訪問介護』とは?
訪問介護とは、高齢者(利用者)とその家族だけでは、日常生活を送ることが難しくなった家族に対して、訪問介護員が『住まい』を訪問して、介護を行ってくれるサービスです。訪問介護員はホームヘルパーとも呼ばれています。
訪問介護の対象となる『住まい』には、自宅のほか軽費や有料の老人ホームなども含まれています。また、介護保険が適用されるサービスのため利用者の負担も少なく以下のような資格を有した介護のプロによるサポートを受けることができます。
【訪問介護員が有している主な資格】
- 介護福祉士
- 介護福祉士実務者研修修了
- 介護職員初任者研修修了
>関連記事:「『介護士』『介護福祉士』の違いとは?有資格者・無資格者それぞれに依頼できる内容を解説」
「それなら、直ぐにでも、何だかのヘルプを依頼したい!親が高齢になり、最近、弱ってきているので・・・。」と思われるかもしれませんが、訪問介護を利用するには条件があるため、すべての高齢者がサービスを受けることができるわけではありません。それでは、どのような手順を踏んで、どのような条件を満たせばサービスを受けることができるのか、次にご説明します。
『訪問介護』サービスを受けるには?
訪問介護は、介護保険サービスの一つであるため、下のフローにあるように、自治体に「要介護認定」の申請をし、「要介護1~5」に認定をされる必要があります。

つまり、訪問介護サービスを利用するには、「介護保険」に認定されるだけでなく、7つの認定区分のうち、「要支援1~2」よりも重度な「要介護1~5」に判定される必要があります。
>関連記事:「一人暮らしの親でも利用できる介護保険適用のサービスとは」
(参照元:介護度とは?要介護・要支援の区分の違いと介護保険の支給限度額を解説 レバレジーズメディカルケア株式会社)
『訪問介護』で受けられるサービスとは
訪問介護には大きく分けて『身体介護サービス』と『生活援助サービス』の2つがあります。
【身体介護サービス:具体例】
・食事介助:食事をする際の支援
・入浴介助:身又は部分浴(顔、髪、腕、足など部分的な洗浄)
・清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔に保つ
・更衣介助:衣類の着脱など着替えを介助
・排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
・歩行介助:自分の足で歩くことができるよう介助
・体位介助:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
・移乗介助:ベッドから車いすに移る際の介助
・移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際の介助
【生活援助サービス:具体例】
・掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
・洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理するまで
・食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
・移動介助:通院時の乗車・降車、受診等の手続の介助まで
・そのほか医療行為でないもの:生活必需品の買いもの、薬の受け取りなど
(参照元:「訪問介護とは?サービス内容や費用など詳しく解説」2022年11月16日 セントスタッフ株式会社/【はじめての方へ】訪問介護とは?サービスの利用方法と費用 株式会社LIFULL)
『訪問介護』に依頼できないサービスとは
訪問介護は、利用者本人が自力ではできない日常的な行動を援助するためのサービスです。そのため、利用者本人以外への援助や日常生活に関係のない行為などへの援助は対象となりません。
具体的には、以下のような内容が訪問介護サービスの対象外となります。
・直接利用者の援助に該当しないサービス
(例)利用者の家族など本人以外のための家事や来客の対応など
・日常生活の援助の範囲を超えるサービス
(例)庭の手入れ、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備 など
訪問介護員は定期的に自宅に来て援助をしてくれるので、ついつい「ついでに・・・」と言って、担当者を困らせるような依頼をしてトラブルにならないよう、ルールを守って利用することが重要です。
(参照元:「どんなサービスがあるの? - 訪問介護(ホームヘルプ)」厚生労働省)
『訪問介護』の費用はどのくらい?
訪問介護における、サービス内容と時間ごとの料金目安は以下になります。原則、利用料の負担割合は1割ですが、所得によって自己負担額が最大3割まで増える場合もあるため、親の世帯収入を確認しておきましょう。また、深夜や早朝など、時間帯によって割増しになる可能性があるため、注意が必要です。
| サービス費用の設定 | 利用者負担(1割) (1回につき) |
|
|---|---|---|
| 身体介護 | 20分未満 | 165円 |
| 20分以上30分未満 | 248円 | |
| 30分以上1時間未満 | 394円 | |
| 1時間以上1時間半未満 | 575円 | |
| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 181円 |
| 45分以上 | 223円 | |
| 通院時の乗車・降車等介助 | 98円 | |
(参照元:「どんなサービスがあるの? - 訪問介護(ホームヘルプ)」厚生労働省)
高齢者の自宅での事故は早期対応が重要!
『訪問介護』は、このように高齢者が住み慣れた家でいつまでも暮らせるよう支援をしてくれる、心強いサービスです。ですが、やはり理想としては親がいつまでも元気に自立して生活をしていることではないでしょうか?
高齢者は自宅での事故が約8割と言われています。しかも高齢になればなるほど重症化しやすく、回復までに時間がかかる、場合によってはそのまま寝たきりになってしまうというリスクも高いです。
>関連記事:「なぜ一人暮らしの高齢者に『見守りサービス』が必要なのか:3つの理由とは?」
そこで、お勧めしたいのが高齢者の『見守りサービス』です。
『見守りサービス』は、一人で実家に暮らす親の生活に異常や緊急事態があった時に、見守る側に通知が行くシステムです。
現在、様々な『見守りサービス』がありますが、現在、親が元気に暮らしている場合、「今、問題が起きている訳ではないので、そこにあまりコストをかけたくない・・・」と思われるのではないでしょうか?
『ひとり暮らしのおまもり』は、そのような方に向けて開発された月額費用無料で手軽に始められる見守りサービスです。
- 工事不要の見守りサービス
- 落とし物防止に使われているIoT技術を採用
- 月額費用がかからず9,240 円(税込)と低額
「実家に一人で住む親のことが心配・・・」と様子が気になってはいても、自分の生活があって、なかなか親にタイミングよく連絡できない、様子を見に帰省できないという方も多いかと思います。
『ひとり暮らしのおまもり』は、親の活動が一定時間ないという異常があった時に、子のスマホアプリに通知が行くシンプルな仕組みです。ですので、子にとっても、日常生活の中で負担なく見守りができます。