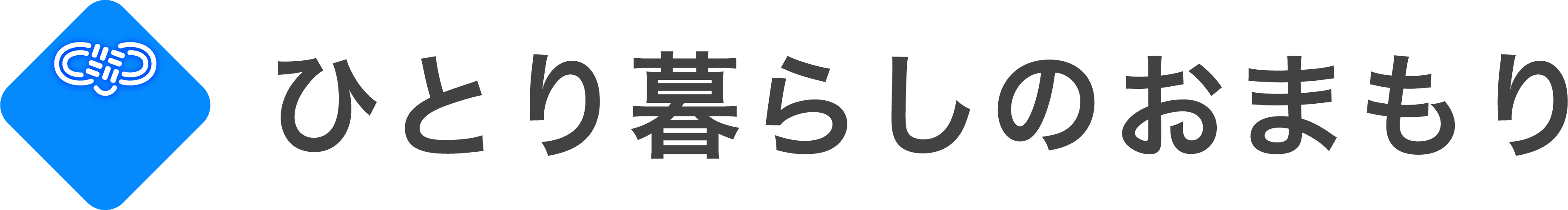親が高齢になるにつれ、以前と同じような接し方では上手く行かず、頭では「親と良好な関係でいたい」「年をとってきたから優しく接したい」と思ってはいても、親と向き合うとついついイライラしてしまい、そんな自分に自己嫌悪を感じ、厳しい態度をとってしまうという悪循環を起こしているという方が少なくないと言います。
場合によっては、親とあまり連絡をとらなくなってしまったというようなこともあるようです。しかしながら、親と疎遠になってしまうと、介護の方針、相続手続きだけでなく、最悪の場合、高齢者を狙った詐欺などの犯罪に巻き込まれてしまうなどの可能性もあるため、単に「仲が悪い」という感情的な問題では片づけられません。
そこで今回は、高齢の親になぜイライラしてしまうのか、その原因と付き合い方についてまとめてみました。高齢の親への接し方でお悩みの方やストレスを感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
見守りサービスという選択肢も!
イライラの原因は理想と現実の“ギャップ”
なぜ、親が年老いて行くにつれて、イライラを以前にも増して感じるようになったのか、自分ではなかなか俯瞰して考えられないものです。心療内科の『あたまこころのクリニック』によると、イライラの原因は「理想と現実のギャップによって生まれる不快感のあらわれ」だと言います。
つまり、子が年老いた親にイライラしてしまう原因の根本にあるのは、「理想=親が若かった頃」と「現実=年老いた親」のギャップにあると考えられます。
そこで、人は年を老いると、どのような変化を体験するのかを、最近の研究からご紹介したいと思います。
1.加齢による身体的変化
人は誰でも老いることで、身体機能が低下し、心理的な変化が起こります。ホルモンバランスの崩れや、認知症などにより、高齢になるにつれ怒りっぽくなる場合もあります。
さらに、肩が痛くて、高いところの物を取れなくなる、膝が痛くてしゃがめなくなり、床に落ちた物を拾えなくなるなど、今まで出来ていた日常的動作が徐々に困難になって行きます。また目が悪くてゴミや汚れに気付かないということもあります。
そのような身体的変化から、久々に実家に帰って「昔は綺麗好きだったのに、帰る度に部屋が散らかっていて、汚くなっている・・・」とショックを受けて、つい親にその状態に対する不満をきつく言ってしまうということもあるようです。
2.加齢による精神的変化
精神機能とは、記憶や注意、認知、感情などを指します。高齢者の精神機能の低下は中枢神経系との関係があるため、個人差が大きいと考えられています。中枢神経系は、脳と脊髄の総称で、全身から集まってくる情報を処理し、指令を発信しています。高齢者の中枢神経系の低下は、様々な要因が複雑に絡み合っていると言われています。
高齢者を中心に診ている『浜辺の診療所』によると、人が年を取るにつれて体験する『喪失感』が精神的変化に大きな影響を与えていると言います。『喪失感』は、仕事の引退、また年老いてから経験する同年代の友人、兄弟、配偶者などの死などから来るもので、重篤な場合、うつ病を誘発する可能性も指摘されています。また、同施設によると、高齢者のうつ病有病率は、比較的軽度なものも含めると、およそ15%だといいます。さらに、高齢化社会が進む中で、今後この割合は、上昇傾向にあると考えられています。
高齢者のうつ病の特徴として、気持ちの落ち込みといった精神的な症状だけではなく、身体の不調を訴えることもよくみられると言います。
さらに、そのような「不安」から安心感を得るためや、自身の存在を周りに認めてもらいたいという気持ちから同じ話を繰り返しするようになると言います。子としては「その話は、何度も聞いたよ」とイライラしてしまうかもしれませんが、特に、若くて元気だった頃の話をすると、自分に自信を取り戻すといった効果もあると言われていることから、老化防止のためと思って話を聞いてあげることが重要でしょう。
3.加齢による知的能力の変化
高齢になるにつれ「なかなか物や人の名前が出てこない・・・。」「だんだんと頭の回転が鈍くなってきた・・・。」などと感じると訴える方が少なくありません。一方で、高齢になっても、様々な趣味や学習などに新たに取り組んで生き生きと過ごしている方も多くいらっしゃいます。
このような知能の差はどのようにして生まれるのでしょうか?『公益社団法人長寿科学振興財団』は、知能を「目的に合うように行動し、合理的に考え、まわりの環境に効果的に働きかけて、問題を解決していく能力」と定義しています。知能は「掃除をする」「買い物をする」「食事を作る」といった日常の行動を支えており、複数の下位要素によって構成されているといいます。
その下位側面の中で大きな割合を占めていると考えられているのが、結晶性知能と流動性知能の2つです。以下にそれぞれの特徴と違いを簡単に紹介します。
| 知能の種類 | 流動性知能 | 結晶性知能 |
| 知能の目的 | 新しい情報を獲得し、それを処理し、操作していく知能。処理のスピード、直感力、法則を発見する能力などを含む。 | 一般的知識や判断力、理解力などで過去に習得した知識や経験をもとにして日常生活の状況に対処する能力。 |
| 先天・後天性 |
生まれながらもっている能力。 |
個人の一般的知識や判断力、理解力、洞察力、過去に習得した知識や経験から習得した知識、教育や学習などから獲得していく知能。 |
| 年齢との関係 | 30歳代にピークに達し、60歳ごろまでは同レベルが維持されるが、それ以降は急速に低下。 | 70歳、80歳になると、なだらかに低下するもののそのレベルは20歳代に近い能力が維待される。 |
後天的な能力である結晶性知能は、 高齢になっても若い頃と実はほとんど変わらないことから、何かを学び習得することが十分可能であることを示しています。一方、情報処理能力、いわゆる「頭の回転の速さ」である流動性知能は加齢に伴い著しく低下して行きます。
ですので、親が言葉が出て来なくて「あれ」「これ」「それ」などの代名詞が多くなり、話していることがわからずイライラするということがあるということがあるかもしれませんが、それは正常な老化性の変化であり、若かった頃のようには戻らないことを理解して、受け入れることが重要でしょう。
4.自分の仕事や生活が忙しい
親と話をしてイライラしてしまう原因としては、自分自身が感じている生活へのギャップが原因であることも考えられます。親が高齢の子世代は主に仕事や子育てがまだ忙しい40、50代です。自分が時間に追われていて精神的、身体的に余裕がない状態で親から頼まれごとをしたりすると「本当は自分の時間を大事にしたいのに」と、思い通りならないことにイライラしていることもあります。特に、忙しく疲れている時に、親が同じことを何度も連絡してきたり、頼まれごとをされたり、怒りっぽかったりすると、イライラしてしまうということもあるかもしれません。
このイライラの原因として、親に対して、若い頃と同じようなコミュニケーションの在り方で接していると上手く行かないということが考えられます。
親の若いころのイメージとのギャップを受け入れられずそのような寂しさの裏返しから親にきつく当たってしまう、また自分の生活に追われて優しくできない自分に自己嫌悪を感じてさらにイライラしてしまうということもあるかもしれません。
自分自身も年を取れば同じような変化を経験すると頭ではわかっていても、つい感情的になってしまうこともあるかもしれません。そこで、親にイライラしないためのコミュニケーションのポイントを、様々な専門家の知見から次にご紹介致します。
(参考:『イライラする時の過ごし方』/『高齢の親との付き合い方はどうすればいいの?良好な関係を築くための方法を解説!』/『高齢者の心理的特徴』/『高齢者における人間関係、こころの健康』/『』/『知能の年齢による変化』/『イライラするのはなぜ?イライラする原因と解消法について解説』/『高齢期における知能の加齢変化』/『流動性知能・結晶性知能とは?その特徴を具体例でわかりやすく解説』)
年老いた親にイライラしないための対策とは
中には、子供の頃から親との性格の不一致があり親との関係が上手く行っていないという人もいるかもしれません。ですが、この記事を読んでくださっているなら、恐らく「高齢の親とお互いに気持ちよくコミュニケーションをとりたい」と思われている方が多いかと思われます。そこで、高齢の親との付き合い方の3つのポイントをご紹介します。
1.高齢者と現役世代との違いを理解する
まず、高齢になった親と現役世代である子との違いを理解して接することが重要です。その違いは主に2つあります。
一つは、先にご紹介したような、心身の衰えです。今までできていたことができなくなって行くという変化を経験しているというのは、本人が一番さみしく感じているという気持ちを理解することが重要です。
もう一つは、時間に関する概念の違いです。介護関連の書籍を多く出版する株式会社リクシス 創業者で取締役の酒井氏によると、年取った親から子への説教は、自分がこの世にいられる期間が残り少なく、その後残された子のことが心配だからこそ繰り返したり、強めに出てしまうと言います。
そのような親の気持ちを理解することで、イライラを少しは軽減できるかもしれません。
2.親子であっても「ありがとう」「ごめんなさい」は言う
脳科学者の黒川氏によると、高齢の親とのコミュニケーションにおいて、「『ありがとう』と『ごめんなさい』のサンドイッチは無敵」だと言います。
常に「ありがとう」と言う
実際に「高齢の両親が何をやってもお礼を言ってくれない」と不満を抱えていたA子さんの事例をご紹介したいと思います。A子さんが、そのような愚痴を友人に話したところ、「親が自分にしてもらったことを考えたら、親孝行をしてし過ぎることはないんだよ。」と言われたと言います。
そして、A子さんは、自分自身も親に対して「ありがとう」という言葉を言っていなかったことに気づき、声に出して伝えるようにしました。
A子さんが、そのように態度を改めたところ、親自身にも同様の変化が現れ、子に何か頼む際に「悪いんだけど〇〇してくれる。」そして何かしたら「ありがとう。」というように変化が現れ、関係性が改善されたと言います。特に、昔気質の80代の父親は、誰に対しても滅多に「ありがとう」という言葉を言わなかったのが、子に対してだけでなく、妻、親戚、そしてレストランや旅先のホテルのスタッフに対しても常に言うようになったと言います。
A子さんは、その変化に非常に驚いたと言い、それを「『ありがとう』と言った方が周囲の人が親切にしてくれるということに気づいたのでは」と話しています。
潔く「ごめんなさい」と言う
現役世代の子にとっては、親に「ありがとう」と言うよりも、謝る方がハードルが高いと感じる方も多いのではないでしょうか。自分の生活が忙しい中、親から色々と頼まれるとついつい忘れてしまう、もしくは手が回らないということがあるかもしれません。そのような時に親から「あれ、やってくれなかったの?」と言われると、ついつい「やろうと思ったんだけどバタバタとしていて……」などと言い訳したくなるかと思います。ですが、順天堂大学医学部教授の小林先生によると「高齢の親に対して、自分に非があるときは、いさぎよく心を込めて『ごめんなさい。』と謝る」ことが重要だと言います。
高齢の親に変わることを期待するのはなかなか難しいです。子自身が高齢になった親への接し方をアップデートする方が、お互いに気持ちよくコミュニケーションがとれるようになり、関係性の改善につながる確率が高いと言えるでしょう。
3.親を尊重すること
親子の関係において、パワーバランスは常に変化をして行きます。先にご紹介した、介護関連の書籍を執筆している酒井氏によると、子が未成年の時は、親が保護者の立場であったのが、子が成人すると均衡し、それが親が高齢になり心身が老いるにつれ、子の方が強い立場になるようになると言います。親は、そのことを受け入れられず、逆に子としては「心配して言っているのに、何で言うことを聞いてくれないんだろう」と感じてイライラが募るということもあると言います。
親の生活を尊重するための例として、高齢者の見守りサービスがあります。高齢化社会が進むにつれ、現在ライブ映像で親の様子を伺えるカメラ型など様々なサービスが選べるようになりました。しかしながら、「子に自分の様子が見られる」ことにパワーバランス的にもプライバシーの意味でも、親が抵抗を感じて高齢者見守りサービスを拒否し、それが原因で親子喧嘩になることもあると言います。
そこで、生活を尊重しながら、さりげなく様子を見守る方法としてお勧めしたいのが、「ひとり暮らしのおまもり」です。「ひとり暮らしのおまもり」は、一日に一度は動かす場所に設置し、動きが一定時間ない異常があった場合にのみ、見守る側の子に通知が行くシステムです。そのため、親のプライバシーを守りながら見守りが行えます。
「高齢の親のことが心配だけれども、自分の生活があってなかなか様子を見に行けない・・・」とお悩みの方は、「ひとり暮らしのおまもり」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
>関連記事はこちら:
『利用者インタビュー「母と離れて住んでいる私の気持ちが少し楽になりました」』
『なぜ「動きが無いとき」にだけ通知がある高齢者見守りシステムがおすすめなのか?:3つの理由とは』
(参考:『高齢の親との付き合い方が分からない方必見!ストレスをためない方法』/『高齢になった親との関係がこじれやすい3つの理由』/『高齢の親にかける言葉の鉄則とは?小林弘幸先生が教えるコミュニケーション術』/『高齢の母親にうんざり…脳科学に基づいたお互いにイライラしない会話術』)
- 工事不要の見守りサービス
- 落とし物防止に使われているIoT技術を採用
- 月額費用がかからず9,240 円(税込)と低額*